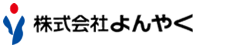今週の1問1答
先進医療Bの申請は臨床実績が必要か?
厚生労働省は7月19日に、先進医療会議を開催しました。この日は、新規技術について審査したほか、「先進医療会議における利益相反の対応」や「先進医療Bの申請に必要な数例以上の臨床使用実績の効率化」について議論しています。 ・・・もっと見る
特定除外制度の見直しとは?
厚生労働省は7月17日に、診療報酬調査専門組織の「入院医療等の調査・評価分科会」を開催しました。この日の議題は、大きく次の3点で、これまでの議論を踏まえて、厚労省当局から新たな論点が示されています。その中で、「一般病棟入院基本料(主に7対1)の見直し」に関しては、まず、厚労省当局から「7対1入院基本料を算定している医療機関は、長期療養を提供するのではなく、複雑な病態をもつ急性期の患者に対し、高度な医療を提供する」という考え方が示されました。 ・・・もっと見る
フリーアクセスにおけるライトアクセスの適切性は誰が判断?
超党派の国会議員有志で組織される国会版『社会保障制度改革国民会議』は7月1日に、最終とりまとめを行い、公表しました。 報告書では、社会保障改革を、(1)国民がガバナンスできる、わかりやすく簡素な制度とする(2)将来世代にも責任を果たせる持続可能な制度とする(3)国民(受益者であり負担者)サイドからの改革が不可欠である―という3原則に立って検討してきたことを強調。医療・介護に関しては、「短期的改革」と「中期的改革」に分けて、改革案を提言しています。 ・・・もっと見る
長期入院型病院、人件費比率高いが薄利多売型で収益力アップ?
厚生労働省は7月2日に、平成23年度の病院経営管理指標を公表しました。 これは、医療法人病院、公的病院、社会保険病院等を対象に、各会計年度における損益状況(損益計算書)、財政状況(貸借対照表)などを集計したものです。医業経営上の問題点改善や、中長期的な展望に立った経営方針策定にあたっての重要資料といえます。 ・・・もっと見る
消費税8%対応、初・再診料や入院基本料等を引上げる方向へ
厚生労働省は6月21日に、診療報酬調査専門組織の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」を開催されました。 この日は、「消費税率8%引上げ時の対応」が主な議題となり、「2段階対応(通常の取引と、建替え等の高額な取引)には、多くの委員が反対している」ことを確認したうえで、厚労省から次の3つ(正確には4つ)の対応案が新たに示されました。 ・・・もっと見る
新成長戦略策定、先進医療拡大や医療サービスの国際展開を実施
政府は6月12日に、産業競争力会議を開催し、成長戦略をとりまとめました。成長戦略は、14日の閣議で決定されています。 さて、成長戦略は、(1)大胆な金融政策(2)機動的な財政政策―に続く、安倍内閣の『3本の矢』の最後の1本にあたります。 「世界の国々がいずれ直面する少子高齢化、資源・エネルギー問題の解決策を提示し、20年以上停滞していた経済を一気に動かす」という基本的考え方に立ち、「日本産業再興プラン」「戦略市場創造プラン」「国際展開戦略」という3つのアクションプランを打出しました。 「戦略市場創造プラン」には、健康増進・予防サービス等の振興などで、2030年に国内で37兆円、海外で525兆円の市場を開拓することが盛込まれました(国民の「健康寿命」の延伸)。 ・・・もっと見る
定期巡回・随時対応型、未参入者は「夜間等対応が困難」と誤解
厚生労働省は6月6日に、社会保障審議会の介護保険部会を開催し、(1)在宅サービス(2)施設サービス(3)介護人材の確保(4)認知症施策―と幅広いテーマが議題となりました。 (1)の在宅サービスについては、平成24年度の介護報酬改定等を受け、各種の「居宅サービス」と「地域密着型サービス」の現状がどうなっているかが、厚労省当局から報告されました。 その中で、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の調査によると、参入事業者と未参入事業者とでは、定期巡回・随時対応サービスのイメージが大きく異なっていることが明らかになっています。 たとえば、未参入では「軽度者には向かない」「夜間・深夜に利用ニーズがない人には向かない」と考えていますが、既に参入している事業者ではそのような考えはごく少数派に限られているようです。 ・・・もっと見る
病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方について
厚生労働省は5月30日に、「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」を開催し、この日は厚労省当局から「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方」案(報告制度案)が提示されました。 社会保障・税一体改革の中で、「効率的・重点的な医療提供を行うために、現在の一般病床を、高度急性期・亜急性期等・慢性期に機能分化していく」方向が示され、これを実現するため、検討会では(1)医療機関が現在保有する自院の機能を都道府県に報告する(2)都道府県はその情報をベースに、地域に必要な医療機能等を定めた「地域医療ビジョン」を策定する(3)地域医療ビジョンに沿って、都道府県内の医療提供体制を構築・調整していく―という制度(報告制度)の議論を続けています。 厚労省案では、制度の骨格について「各医療機関(有床診療所含む)は、『病棟』単位で、自院の医療機能の「現状」と「今後の方向」を都道府県に報告する」こととしています。 ・・・もっと見る
今後の亜急性期医療に求められる機能とは
5月30日に、診療報酬調査専門組織の「入院医療等の調査・評価分科会」を開催しました。 【亜急性期入院医療管理料】の課題等を探ったうえで、今後の方向性等について議論されました。 厚労省の資料によると、【亜急性期入院医療管理料】を算定する病床の入院患者の状況は、次のように整理できます。 ●骨折など整形外科疾患が多いが、疾病構造の特徴は見られない ●重症度・看護必要度は、13対1一般病棟や回復期リハ病棟の入院患者に比べて低い ●1ヵ月あたりのレセプト請求額は、13対1一般病棟の入院患者よりも高い このため、委員からは「亜急性期入院医療管理料の患者像が明確でない。機能等を明確にすべき」という意見が相次ぎました。 ・・・もっと見る
今後、在宅医療でニーズが高いと思われる専門分野は?
今後、ますます高齢化が進む我が国の高齢者医療は、在宅医療へシフトせざるを得ない状況となっています。 2012年度の診療報酬改定では、約5500億円の財源のうち、約1500億円が在宅医療に重点配分され、2014年度の診療報酬改定でも、推進されると予想されています。 その中で現在の在宅医療は「内科系」や「がん医療」に焦点が当てられているように感じますが・・・ ・・・もっと見る